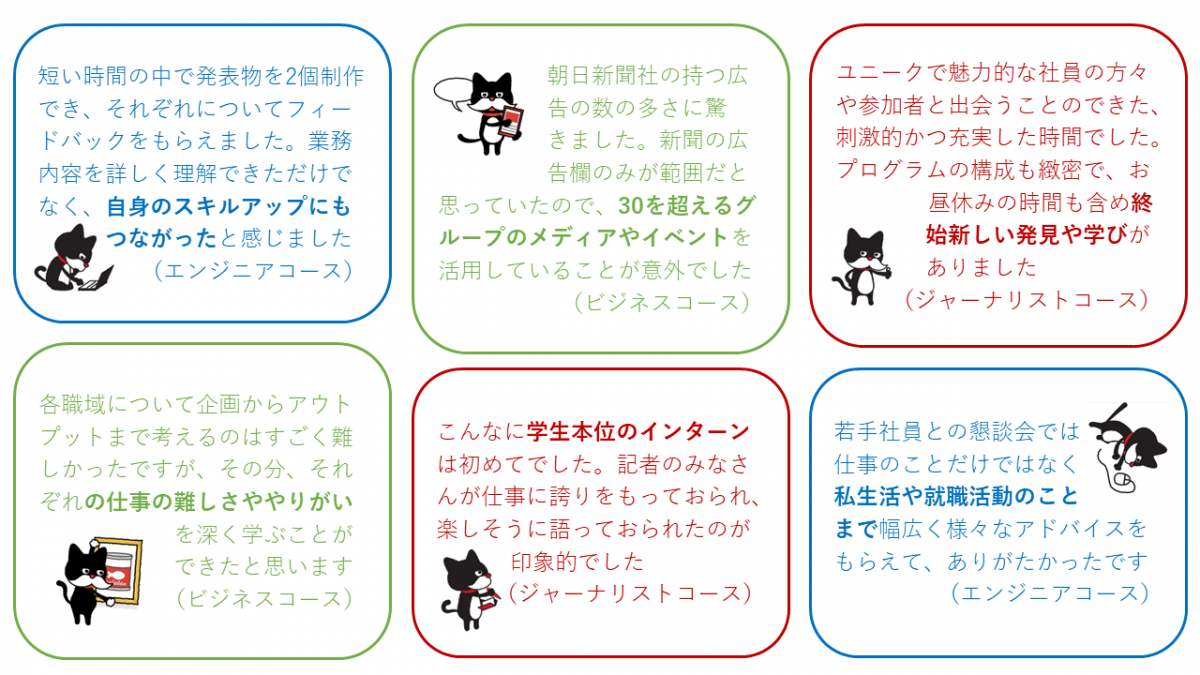Internship インターンシップ


2027卒向けのインターンシップは終了しました
2026年夏には、28卒の皆さん向けに夏インターンシップを開催します



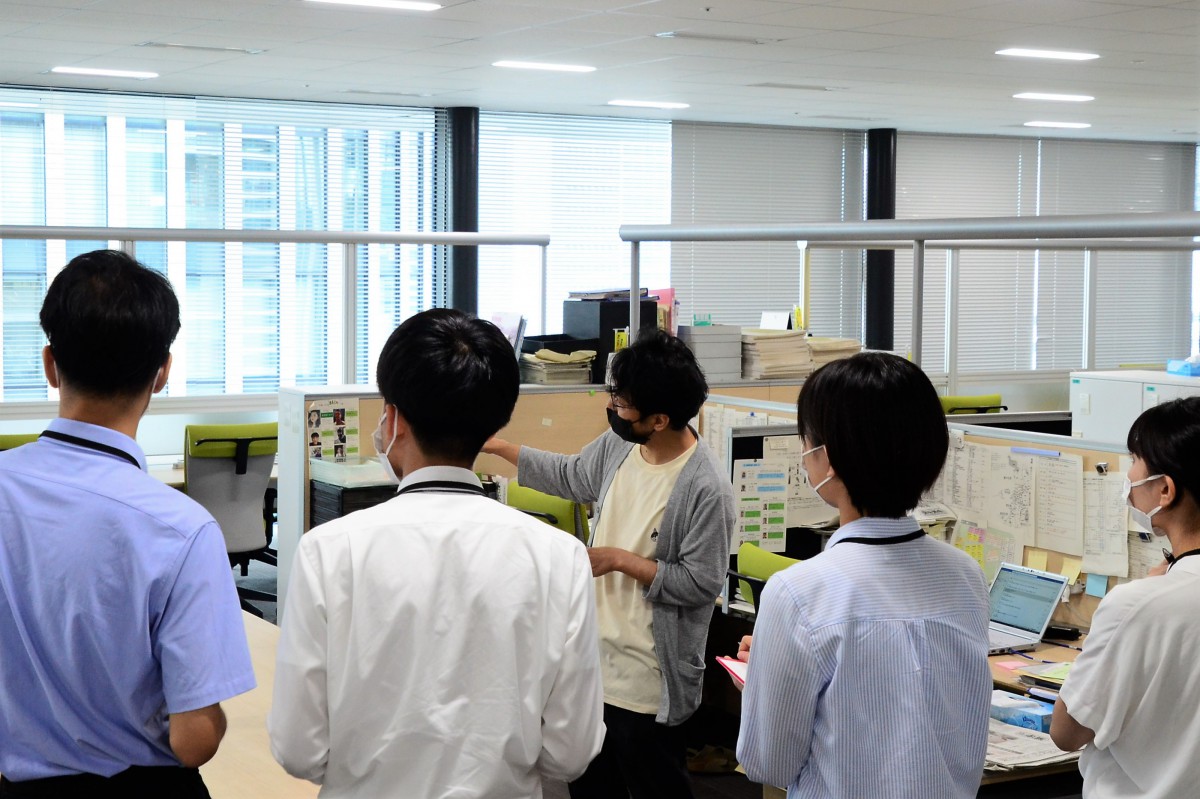


職場を知る -会社見学-
どんな環境? どんな設備がある?
社員の雰囲気もぜひ見てください



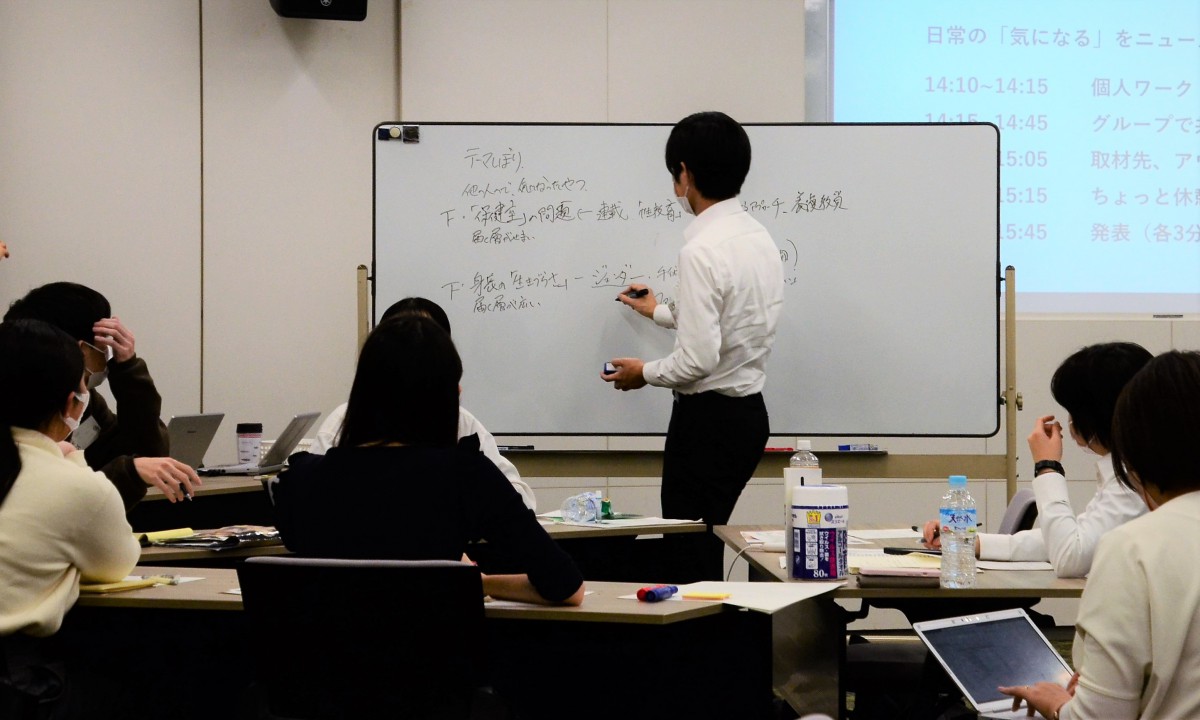
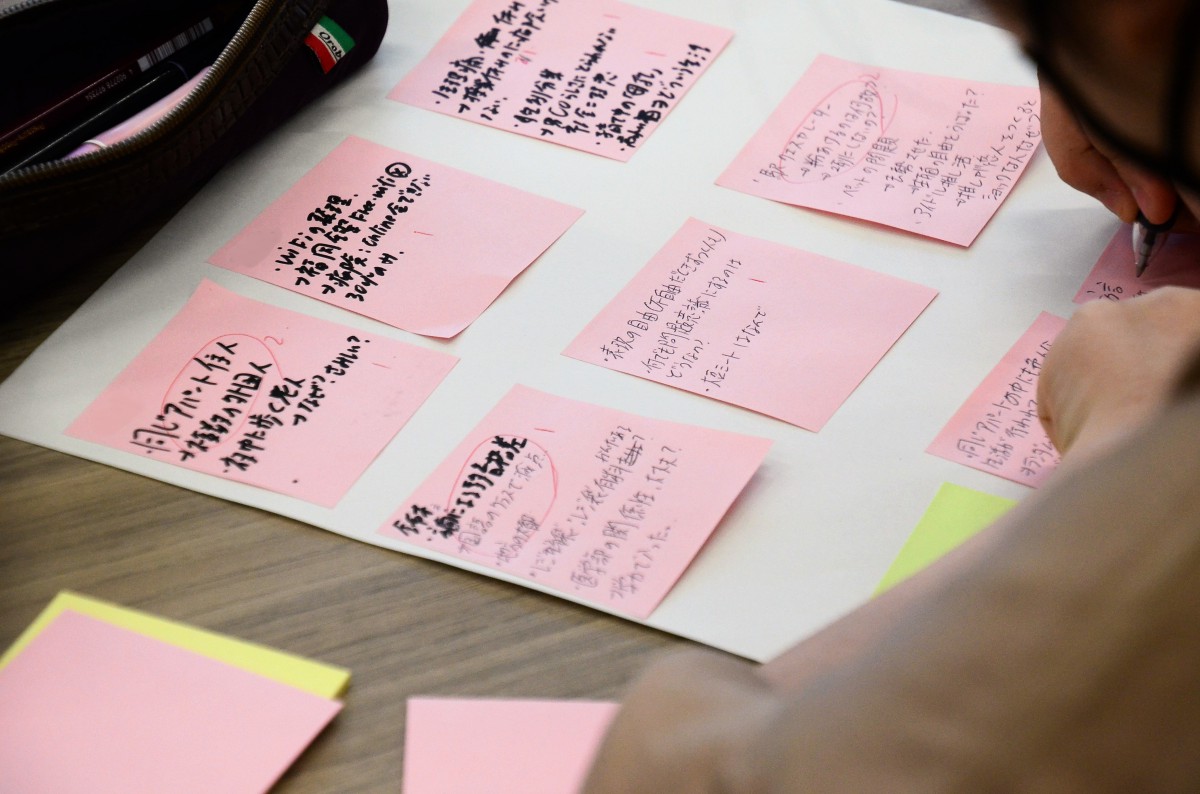

仕事を知る -体験ワーク・グループワーク-
新聞社にはさまざまな職種があります
あなたの“得意”や”好き”と合う仕事が見つかるはず



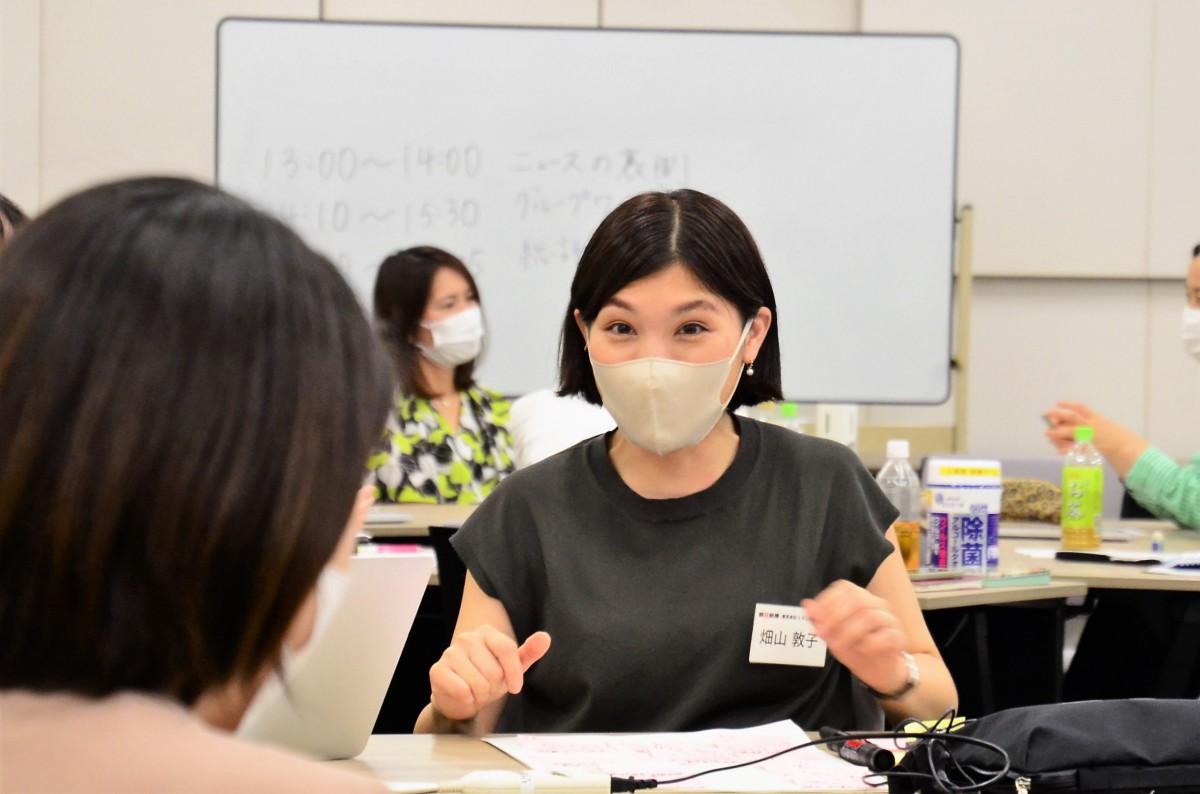


社員を知る -グループトーク-
若手、中堅社員と話す時間を多くとっています
気になること、遠慮なく聞いてくださいね
ここがポイント
参加までの流れ
交通費は原則、マイページに登録された自宅を起点に計算します。応募多数の場合、オンライン面接を実施することがあります。参加していただく場合、誓約書の提出をお願いすることがあります。
参加者の感想
日程・プログラム
詳細は確定次第、こちらで随時お知らせします。ご応募は全て28卒マイページで受け付けます
| 【28卒向け】ジャーナリストコース 3days | |
|---|---|
| 日程・会場 | 2026年8月 東京本社、大阪本社 |
| 内容 | 取材・執筆体験(フィードバックあり)、ニュースの現場がわかる講演、記者とのトーク など |
| 【28卒向け】ビジネスコース 5days | |
|---|---|
| 日程・会場 | 2026年8、9月 オンライン+東京本社 *5日間のうち、前半はオンライン開催、後半は東京本社での対面開催を予定しています |
| 内容 | ビジネス部門の幅広い仕事を知るセミナー、現場社員との多彩なワーク、社員とのトーク など |
| 【28卒向け】エンジニアコース 1day | |
|---|---|
| 日程・会場 | 2026年8月 東京本社 |
| 内容 | CMSによるメディアサイト作成、IT技術活用のアイデアソン、社員とのトーク など |
この他にも、記者部門と技術部門で職種・仕事別のインターンを開催予定です